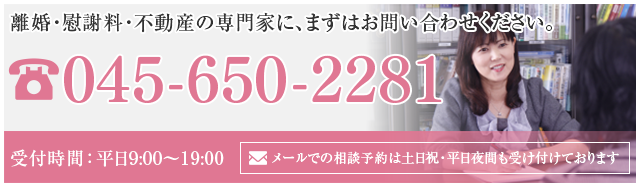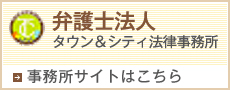経営者の離婚相談
Contents
1 経営者等(取締役等)の離婚の特徴
経営者等(取締役等)(以下では単に「経営者等」といいます)(※0)の方から離婚に関する法律相談を受ける機会は多いです。職業別で見ても経営者等の方は夫婦関係がうまくいかず、最悪、離婚に至るケースも多いものと言えます。
その理由は、概括的に言えば、ほとんどの経営者等が激務であり、職務に懸命に励んでいる方ほど、家庭での時間が少なくなってしまうからではないでしょうか?これは男性か女性かに関わりません。
激務であることを前提に夫婦相互に理解し合えて夫婦関係も調整が効けば理想ですが、残念ながら、なかなか理想どおりにはいかず、すれ違いになる夫婦が多いという特徴があります。
※0 会社等の経営者(取締役等)等の他、高所得者(自営業・芸能人・プロスポーツ選手)等も一般的には含んでも良いものと思われます。
2 経営者等の離婚において最も問題となること
離婚の際に検討すべき問題点として、①親権・監護権②養育費③財産分与④未払婚姻費用⑤慰謝料等がありますが、経営者等の離婚の際には、収入が多いことから通常は有する資産も多いため③財産分与が最も問題となります。
詳細は「経営者等の離婚・財産分与について」の欄にて述べますが、経営者等は一般のサラリーマン等に比べてその収入に対する経営者等本人の能力が貢献する割合が高いため、通常の財産分与のように婚姻後の収入から築き上げた財産の2分の1を分与する必要があるのか、という点が問題になるわけです。
3 経営者等の離婚・財産分与について
(1) 財産分与の割合について
【経営者等以外の方等通常一般人の場合】:2分の1ルール=夫婦(共有)財産(※1)の2分の1は分与の対象になります(清算的財産分与)。
※1①夫婦(共有)財産とは?→夫婦になって(正確には入籍して)から、夫婦が相互に協力することで築き上げた財産のこと。法律上も共有と推定されます(民法762条2項)。逆に、夫婦になる前から持っている財産及び夫婦になってからでも、夫婦の相互の協力でなく取得した財産は、②「特有財産」として、夫婦(共有)財産にはなりません(同条1項)。
この点、条文上は「婚姻中自己の名で得た財産」と、あたかも取得名義を基準にするかのようですが、敢えて夫婦の片方の名義にした場合はもちろん(※2)、どちらか片方名義での取得でも、例えば勤労して得る給与所得のように、夫婦が相互に協力することで得られる収入等については、上記②の特有財産ではなく、①の夫婦(共有)財産となります。
※2 上記1項の規定は、夫婦がその一方の財産を合意の上で他方の所有名義とした場合にまで、これをその所有名義人の特有財産とする趣旨ではない(最高裁判決昭和34年7月14日民集13-7-1023)。⇒結局、上記①の夫婦(共有)財産→2分の1分与することに。
②の特有財産→分与の必要はない(なお、特有財産からの利子や配当についても特有財産として分与の対象とはされないことが通常)ことに。その判断基準は、所有名義だけでなく、《(取得原因等)共同財産に対する夫婦の寄与の程度、婚姻中の協力及び扶助の状況、職業、収入その他一切の事情から、ある程度実質的に考慮される》ことに。
⇒この《(取得原因等)共同財産に対する夫婦の寄与の程度、婚姻中の協力及び扶助の状況、職業、収入その他一切の事情から、ある程度実質的に考慮される》ことが、配偶者の片方が高収入、かつ特に経営者等、その高収入が特殊な力に基づいている場合の財産分与における実質的公平な判断に結び付いていくわけです。
【経営者等の方の場合】:必ずしも上記2分の1ルールに基づきません。裁判例でも、上記《取得原因から、ある程度実質的に考慮される》という判断基準から、医師(経営者等)の場合に、夫婦(共有)財産でも分与割合を2分の1としない判断が示された例があります。
A 例1(福岡高等裁判所判決昭和44年12月24日判例タイムズ244号142頁)=夫が医院を経営していたケースですが、夫の経営者等ないし病院経営者としての手腕、能力を高く評価し、経営につき一人で采配を振るっていたこと、実質上の出資者も夫のみであったこと等から妻の貢献度は低いものと判断し、妻が2分の1ルールを主張し要求した2億円ではなく、その10%の2000万円のみを認めました(前提として、医師資格取得のコストは個人の資質・負担であることは当然と考えられているものと思われます)。
B 例2(大阪高等裁判所判決平成26年3月13日判例タイムズ1411号177頁)=原則として、夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当であるが、高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成され、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成された場合などには、そうした事情を考慮して寄与割合を加算することを許容しなければ、個人の尊厳が確保されたことになるとはいいがたく、夫が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたこと、婚姻後に医師資格を活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割とすることは合理性を有すると判示して、2分の1ルールを修正しました。
C 例3(東京地方裁判所平成15年2月25日)=夫が会社経営をしていたケースにおいて、妻の寄与度を3割と判断した裁判例があります。
D 例4(松山地方裁判所西城支部判決昭和50年6月30日)=妻が婚姻後家計を助けるためにプロパンガスの販売を始めたところ、営業が順調に伸びていき、支店を設けるまでに発展させました。これに対し、夫は勤めを辞め、この営業に加わったが、やがて酒におぼれ、妻子に暴力を振るうようになり、妻は子どもを連れて別居し、子どもを独りで養育した事案において、裁判所は、妻が長期間忍従を強いられながら夫婦財産を構築してきたその尽力の程度、子の養育に捧げてきた費用等を考慮し、財産の70%を妻に分与しました。
E 例5(東京地方裁判所判決平成15年9月26日)=夫は、一部上場企業の代表取締役をしており、婚姻期間中に得た収入は約220億円と非常に多額でした。一方で、妻は、専業主婦でした。そのため、裁判所は、巨額の収入は、夫の手腕・努力によるものであり、妻の貢献度は低いという判断をしました。
その一方で、婚姻が破綻した原因が主として夫であること、妻が今後職業に携わることを期待できず、今後の扶養的な要素も加味すべきことを考慮しました。結論としては、夫の妻に対する財産分与の額は、夫婦の共有財産の価格の合計である約220億円の5%である10億円と判断しました。
F 例6(長野地方裁判所判決昭和38年7月5日)=料理営業を目的とする会社でしたが、実際は、税金対策のために設立したに過ぎない会社について、法人財産を夫の潜在的な財産と認め、その寄与度2分の1として、扶養的な財産分与も踏まえて、妻に対し1200万円の分与を認めました。
G 例7(大阪地方裁判所判決昭和48年1月30日)=夫が飲食店の営業をしており、法人名義で登記をしている建物があった事例で、裁判所は、法人ではあるものの、個人営業と同視し、財産分与の対象としました。
(2) 財産の調査・評価方法について
【経営者等以外の方等通常一般人の場合】:一般的には、分与対象財産としては次のようなものが考えられます。
① 不動産…自宅住居またはせいぜい賃貸用マンション等、住宅の場合がほとんどと考えられます。別居時点の時価-(同時点の)住宅ローン残高が、分与対象とされます。仮に上記住宅ローン残高が上記時価を上回ってしまう場合には、負債(マイナス財産)の分与(負担)の問題となります。
② 預貯金…婚姻時(a)と別居時(b)の各残高の差額(b-a=通常はプラス)をもって分与の対象とされます。
③ 保険類(生命保険・学資保険等の積立(貯蓄)型のもの)…解約返戻金がある場合、上記②と同様に婚姻時と別居時の各残高の差額をもって分与の対象とされます。
④ 株式、出資持分などの有価証券…上場企業の株式等、売却等処分が可能であることにより流動性の高いものがほとんどと思われます。あと、ゴルフが趣味の方であればゴルフ会員権も考えられますが、最近では、実質的に財産的価値のあるゴルフ会員権自体、本当に少なくなってきております。
なお、ゴルフ会員権を譲り受けた場合、ゴルフ会員権の名義書換手続をする必要があり、その際、名義書換料その他諸費用が掛かります。これらの費用をどちらが負担するかについても事前に明確に定める必要があります。
(条項例)
・甲は、乙に対し、離婚に伴う財産分与として、甲名義のゴルフ会員権(○○カントリークラブ 会員番号×××××)を乙に譲渡する。
・甲は、乙に対し、前項のゴルフ会員権の名義書換手続に協力する。ただし、名義書換手続費用は乙の負担とする。
⑤ 自動車…自家用車がほとんどと考えられます。別居時点の時価-同時点のオートローン残高が分与の対象となります。仮にオートローン残高が上回る場合は、上記住宅ローンについてと同じです。
⑥ 家財道具等の動産類…家財等は、現在では、分与の対象として分けるべき財産的価値よりも、現実に取得でき使用できる利益の分の帰属と、他方、処分する際の処分費用の負担が問題となる程度の扱いに過ぎません。
⑦ 将来の財産(退職金や年金等)…別居時における支給額が計算できるものについては、積立期間に占める婚姻期間の割合により按分した金額が分与の対象とされます。
⑧ 婚姻費用の未清算分…婚姻費用のところで清算されるべき問題なのが原則ではありますが、未払婚姻費用も、離婚時にまとめて支払う場合には結局、離婚時に清算される財産分与と併せて計算されることになり、未払婚姻費用と財産分与間で、金額的に調整されることもあります。
【経営者等の方の場合】:上記①ないし⑧についても、経営者等の場合には、次のような各特徴があるとともに、それ以外にも、下記のアないしクのような特色があります。
① 不動産については、自宅以外にも投資用不動産を所有している経営者等の方等も多くいらっしゃいますので一応、「財産分与」の対象となるか、注意が必要ではありますが、特有財産なのか夫婦共有財産なのかの区別の基準は経営者等以外の一般の方と同じで、上記のとおりです。
不動産に関しての経営者等の方特有の問題として、例えば会社と自宅が同じ場所で同じ建物を使用しているような場合の所有関係があります。
結局は、自宅部分と会社部分とを土地・建物として物理的に分離することができるのか、の検討から始まります。それと同時に所有者が誰(会社・夫・妻・どちらかの両親等)なのか、が問題となります。
所有者は、本来は取得の対価を誰が支出したのかにより実質的に決められることになりますが、少なくとも裁判所等は登記等の形式をまずは重視するので、支出等による実質と登記等の形式は極力合わせておく必要があります。
登記等の形式どおりとした場合には、上記の夫婦共有財産として財産分与の対象となる場合があると同時に、この対象とならなくても、夫婦やその親族の共有関係にある場合には、共有物分割の問題となり、協議→(調停等)→訴訟の流れで解決していくことになります。
なお、不動産や株式を財産分与した場合には、分与した側(通常は夫側が多いものと思われます)に、分与した財産に相当する金額分の譲渡所得が発生したものとして譲渡所得課税がされ得るので、特に高額となる場合には注意が必要です。
② 預貯金については、一般の方と余り変わらないものと思われます。但し、特に経営者等の場合には、会社等が法人であれば名義で形式上分けられますが、法人でない個人営業の場合には、事業所自体の財産と、配偶者個人の財産が混在している場合があり得ます。
ただ、個人事業の場合には、例えば事業所名の通帳を作成して、きちんと社長等経営者の報酬ないし給与等も含めて形式上も分けて入出金等の処理をしている場合にはまだしも、それすらもしていなければ夫婦共有財産の対象の預金がどこまで含まれるのかが判然としない場合もあり得ます。
形式上判然としない場合には、最後は実質的に判断せざるを得なくなります。この場合には、基本的には、婚姻中に増えた預金のうち、配偶者の貢献(=寄与)によるものがどれ位あり、かつ、その貢献(=寄与)の程度はどれ位なのか、という点がポイントになります。
特に預貯金等については、夫婦の共有財産を特定するまでに時間がかかることが多いため、話し合い等も長引きがちです。しかし、話し合いが長引いた場合、会社の経営への影響を無視できません。会社の運営に支障をきたさないためにも、トラブルが生じる前に一度弁護士に相談しておきましょう。
③ 生命保険等の保険についても、一般の方とそれ程変わらないものと思われます。但し、収入も多いことから、掛捨型の保険だけでなく、積立型の保険も多くなることから、別居時における「解約返戻金」の金額もそれなりに多くなる可能性が高いという特色はあります。
また、会社等法人の多くは、将来、役員が退任するときに退職金を支給するために会社等法人を契約者、役員を被保険者とする生命保険(長期平準定期保険や逓増定期保険等)を契約していることが多いです(個人事業主や中小企業の場合、小規模企業共済に加入している方も多いです)。これは会社等法人及び役員の節税目的(※3)からですが、上記保険の場合、契約者が会社等法人であれば、原則として解約返戻金を夫婦の共有財産に含めることはできません。
しかし、上記保険は満期を退職時に設定することが多いことから、別居時における「予定退職金」として、上記解約返戻金に近い金額が財産分与の対象に含まれることはあり得るものと思われます。
※3 例えば、経営状態の良好な会社等法人であれば役員報酬として支給してしまうより保険料として支払っておけば、保険料の、保険の種類によっては全額(但し、かなり特殊な保険。通常は2分の1)から4分の1程度を経費として損金処理できます。
また受領する役員側も、所得税(報酬がそれなりの多額だと累進課税なのでかなり高額の税負担となります)の対象となるよりは、報酬として支払われるべき分の一部を保険料として積み立てて貰い退職時に受領すれば、「退職金」として所得税の優遇措置を受けられます。
④ 閉鎖(非公開(非上場))会社の場合
株式等有価証券に関しては、特に経営者等に多く見られる問題として、会社等法人への出資持分という問題があります。例えば会社等法人の業績が良ければ、その出身持分の価格も高額になる可能性があります。
しかも、会社等法人が事業所の不動産といった高額資産を保有していることが多いため、1口あたりの評価額が高額になる可能性があります。
例えば、株式会社の非公開会社の場合、純資産÷出資口数がその出資1口の形式的な評価額となりますが、この価額を、その持分の流動可能性や、会社の将来の発展可能性等諸要素を加味して評価し直した実質的な評価額をもって本来の価額と見ることが多いです。閉鎖会社の場合には、将来の発展可能性等は個別具体的事情次第でしょうが、流動可能性の点では、持分の譲渡等に対する規制(※4)がある分、低評価にならざるを得ない面はあります。
あと、夫が役員で社長、妻が役員の場合に、離婚時の財産分与により妻の出資持分が清算されなかった結果、離婚後も妻が出資者として残り続けるとどうなるのか、という問題があります。
出資者は社員として、会社等法人の経営について提案したり議決する権利を行使できることになります。また、計算書類の閲覧・謄写等を求めることも、出資の払戻請求をできたりもします。
よって、離婚後も出資者=社員として上記のような権利行使がされたりすることがないように、離婚時に妻の出資持分については、例えば財産分与の対象とした上で、出資持分を買い取る等して円満に解決しておくことが必要になります。
なお、医療法人の場合ですが、平成19年の医療法改正以降は、法人の「社員」であっても「出資持分」はないという形態に統一されています。そのため「出資者」と「社員」が必ずしも同一でない、という場合も多くみられます。
いずれにせよ、当該会社等法人の制度設計によって詳細は異なってきますので、その正確な把握が不可欠です。
※4 会社法上の、株式の譲渡制限(=取締役会の承認)があります。この取締役会の承認と会社に対する株式買取請求については、会社法に詳細に定められています(136条以下)。なお、医療法人に関してですが、本件の医療法人が、法人としての実体を有する医療法人であることや医療法の規定内容を考慮し、同法人の保有資産を夫婦という個人間で全て清算して分配するかのごとく取扱うのは相当とはいえず、同法人の保有資産を財産分与の基礎財産とすることはできない、とした裁判例があります。【大阪高等裁判所平成26年3月13日判決・判例タイムズ1411号177頁】
なお、閉鎖会社についての、夫婦間での譲渡方法は次のとおりとなります。
あ 株券発行会社の場合:株式を財産分与するとの意思表示に加えて株券の交付が必要となります。
い 株券不発行の場合:株式を財産分与するとの当事者間の意思表示だけで株式譲渡の効力が生じます。
う 公開(上場)会社の場合
現在、全ての上場会社の株券は電子化されており、株主の権利は、証券会社の口座(特定口座)で電子的に管理されることになっています。
その為、財産分与をして上場会社の株式を譲り受けることになった場合、当該譲受人は、証券会社に自分名義の口座を有していることが必要となります。
(条項例)
・甲は、乙に対し、離婚に伴う財産分与として、○○株式会社の株式100株を譲渡する。
・甲は、乙に対し、前項の株式を平成〇年○月〇日限り、甲名義の口座(○○証券株式会社●●支店口座番号×××××)に振り替える方法により引き渡す。
⑤ 自動車についても、個人名義のものであれば財産分与の対象となる点等は一般の方と余り変わりません。しかし、経営者等をはじめ高収入の方は、特に男性の場合、高級車を保有することが多く見られます。景気が良いときには、例えばフェラーリやポルシェ等の高級車が、たとえ年式が古くても、いわば次の⑥の骨董品のように予想外の価値を有していたりする場合があり得ます。
よって、特に年式が古い高級車については、専門家等によるきちんとした査定により評価されるべきです。近年では、中古車(や中古の船舶・航空機等)の減価償却期間が「3年と非常に短期間」であることを利用した節税対策も採られていて、特に経営者等の高額所得者は、このような節税策のためにも高額の中古車等を保有していることが多いため、注意が必要です。
(条項例)
・甲は乙に対して、離婚に伴う財産分与として、別紙目録(省略)記載の自動車を譲渡する。
・乙は甲に対し、前項の自動車につき、本日付け、移転登録手続をして、甲はその手続に協力する。
⑥ 家財等についてであれば、一般の方とそれ程変わらず、それ程重要視されないものと思われます。但し、経営者等に限らず高収入の方の場合、夫婦の一方が高価な時計、宝石等の貴金属、絵画、骨董品等を保有している場合があります。
これらがある場合には、きちんと適切な鑑定人等による鑑定評価をして貰い正当な時価が算出されることが望ましいということになります。
⑦ 退職金については、高所得者のうち、サラリーマンや公務員の方と余り違いはないものと思われます。ただ、金額が多額になるであろうことと、支払われる蓋然性が高いであろうことが特色でしょうから、財産分与の対象に含められる可能性はより高いといえます。
問題は、経営者等自営業の方の場合、一般的に「退職金」等は支払われないように思われがちです。しかし、会社等法人化していて、同法人の役員になっている場合には、上記③で述べたように退職金に充てるための生命保険(の解約返戻金)を会社等法人が契約しているケースが多いです。
かつ、上記③のとおり、業績のよい会社等法人程、法人と役員双方にとって税務上の特典が大きいため、多額の保険料を支払い、退職時には多額の退職金が支給されることが規定されている場合が多いです。よって、経営者等の方の場合でも、特に法人化している場合には、退職金も財産分与の対象として要検討となります。
⑧ 未払婚姻費用については、特に経営者等の方のように高収入の方の場合には、支払うべき婚姻費用が多額となるために、離婚までの期間が長いと、婚姻費用の負担が多額となり、かつそれが「未払分」として一度に請求されると想定外の負担となる、という問題が生じます。詳しくは経営者等の方の場合の婚姻費用のところで述べます。
最後に、経営者等の方の場合の財産分与について、ポイントをまとめておきます。
ア 収入が多い→資産の種類も総量も多くなります。
イ 自宅だけでない→自宅と事業所の建物が一体となっていることも多いです。
ウ 会社等法人が存在する場合も多い→法人資産と個人資産が混在することが多いです。
エ 個人から会社等法人への出資が存在する→出資も有価証券等と同じく財産分与の対象になり得るが、価格の評価は難しい。また、特に離婚が問題となってからの出資等であるなら、個人資産からの逃避ではないか問題に。→例えば夫が、(たとえその目的が節税だったとしても)婚姻中から、敢えて個人名義での蓄財を避けて法人名義での蓄財をしてきたことが証明された場合には、夫婦財産として財産分与の対象となることも。
→役員の報酬額の設定の仕方や(=額の変動が会社等法人の利益の変化と適合しているか)出資の内容(=頻度や金額等の「程度」と出資者の収入額とのバランス等)やタイミング(=会社等の機材等の購入等、資金の必要があるときと合致していないか)の調査・分析を、会社等法人の申告書・決算書や会計帳簿等の計算書類(=経営状況が判る書類)と過去の類似裁判例から行うことが肝要になります。
オ 個人(夫・妻その他家族)が会社等法人の役員(委任関係)や従業員(雇用関係)になっていることが多い。→委任契約、雇用契約からの問題が、離婚とは別途問題になります。これについては経営者等の方の場合のところで詳しく述べます。
カ 夫・妻いずれかの「実家」から事業所への資金援助が行われている場合も多い→資金援助の形態が問題に(貸付・出資・贈与のいずれか)。…婚姻中から、極力、上記の3つのどれか明らかになるよう書面等で準備しておくべきです。
なお、特に「貸付」の場合には、それが会社に対するものなのか、夫や妻個人に対するものか、により、税金上の扱いも含めて複雑な処理が必要となることもありますので、弁護士や税理士にご相談ください。
キ 夫・妻その他家族が、事業所等への貸付金融機関に対し保証人になっている場合が多い→離婚するにあたり、保証関係の整理もできるのか、問題に。保証人はあくまでも金融機関との契約関係であるので夫婦・離婚関係とは別→しかし離婚後も保証関係が残ることは望ましいことではないため、離婚条件の中に「(連帯)保証関係を解消するように金融機関と最大限の交渉をすること」を相手方の義務として認めさせるように交渉することが重要となります。
ク 例えば妻の父が会社を営んでいる場合に、会社の後継者として夫が迎えられることから、婚姻と同時に夫と妻の両親との間で養子縁組がされることがままあります
(または相続対策のために、会社を営む夫の両親との間で、妻が養子とされることもあります)。→離婚するだけでは当然には離縁にはなりません。離縁も協議→調停→裁判と、離婚と同様の手続を要します。
→特に相手方との離縁協議が整わないような場合には、専門家である弁護士が代理人として介入して上記の各手続を進めた方が円滑にいく場合も多いです。離縁がなされていないと、将来、離婚した妻の両親の扶養を養子となった元夫が求められたり、あるいは元夫の両親から養子となった元妻への相続が発生するなどの諸問題が発生してしまいます。
財産分与の対象財産や婚姻費用・養育費算定の基礎となる収入資料収集のための
【財産調査について】:調査方法には、次のような各方法があります。
A 弁護士法23条の2照会による金融機関への直接の照会
各金融機関には回答「義務」までが一般的に認められる訳ではありませんが、守秘義務や個人情報保護義務等、開示しないことについての正当な理由がないにもかかわらず回答を拒否したことにより照会者(=弁護士)ないしそれへの依頼者に不利益が生じた場合には、損害賠償義務を負うこともあり得ます。
→照会先各金融機関は開示することによる不利益(=開示された者からのクレームや損害賠償責任の追及)と開示しないことによる不利益(=開示を求めた者からのクレームや損害賠償責任の追及)を天秤にかけて、開示するか否かを決定することになるものと思われます(比較衡量論)。具体的には、財産等の個人情報を、離婚という差し迫った場面においても各金融機関がどこまで守るか、という判断になります。
しかし、実務的には、単なる離婚の際には、財産の開示を求められた側の同意がなければ開示されないのが基本です。そのために、次のBの裁判所を通した照会手続が必要かつ重要となる場合が圧倒的に多くなります。
なお、このAの方法は、裁判所等、両当事者が平等にアクセスできる手続が保障された制度ではないことから、相手方に秘密裡に調査を行い、その調査結果を当方のみが取得したい場合は、このAの方法による他ないことになります。
B 裁判所を通した照会手続
開示を求める者が裁判所に申し立てをして、その申立てを正当と認めた裁判所が各金融機関に対して直接照会等していく次の制度があります。
a 調査嘱託・文書の送付嘱託
預金履歴等について、存否の調査と存在する場合には履歴の写等の裁判所への送付を求める手続きです。銀行等の場合、預金先を各支店ごとに特定して申立てる必要があります。また、金融機関によっては、記録の保存期間や開示に応じる期間を内規等で定めていることが多いです。
開示は、申立時から10年程度遡及した時点までしか応じて貰えないのが最近の一般的な扱いではありますが、裁判所を通じた場合には、記録が残っていれば開示に応じて貰える場合もあり得ます。
なお、嘱託の結果回答される調査結果や送付文書は、嘱託先から、全て一旦裁判所に送られることになります。
よって、裁判所から各当事者に回答や文書が到着した旨の連絡がなされ、通常、当事者は調査結果や送付文書を閲覧・謄写して情報を入手することになります。
このように当事者が平等に扱われる反面、相手方に秘密裡に調査等をしたい場合には利用できないことになります。
b 証拠保全
訴訟等提起前(通常は。提起後もできない訳ではない)に予め保全の必要性について証明して、保全方法として預金履歴の写等を入手しておく方法です。訴訟等を提起してからだと訴訟の相手方によって証拠を隠滅される恐れが高い等の悪質な事案に対しては効力を持ち得るものと思われます。
c 文書提出命令・当事者照会
訴訟等の相手方が文書の提出義務を負うものと判断される場合には、提出を求める者からの申立てと法律上の提出義務の証明により、その者に対し、訴訟手続中に当該文書を提出することを裁判所から命じて貰えます(文書提出命令)。似た制度として、提出義務までは認められないが、それなりの法律上の根拠が認められれば裁判所から照会に応じるよう促して貰える制度もあります(当事者照会)。
各効果として、文書提出命令の場合には、命令に反して提出されない場合には、法律上、当該文書が提出されたものと同じ効果を認めた上での事実認定等がなされます。
当事者照会の場合には、照会に反して回答されない場合には、応じない当事者は照会された情報について、自己に不利な事実を有しているものとの裁判所の心証を事実上(ただし、実務上はかなり有力に)形成されます。これらが、次のCに繋がっていくわけです。
C 資金の流れが説明できなければ、結局、「隠し資産」があるものと認定されることも。
上記の各照会手続や文書提出命令・当事者照会手続等によっても、資金の流れを説明できない当事者は、自己に「不利な事実」を隠しているものと多くの場合に裁判官は心証形成するでしょう。その結果、夫婦の他方当事者には言えない資産、いわゆる「隠し資産」があるものと認定される可能性は非常に高くなります。
(3) 経営者等の方の場合の特色について
① 開業にあたっての出資
→配偶者の片方から受けた出資の清算について
② 会社を手伝って貰っている配偶者の処遇について→離婚に伴い退職させることはできるのか?…合意退職か解雇か?
〔結論〕多少の「解決金」等の金銭を支払っても、「合意退職」を目指すべき!
〔理由〕配偶者が経営者等個人または会社の従業員として雇用されている場合には、仮に配偶者であっても、同人との間には「雇用契約」が締結されていることになるので、解雇するためには客観的・合理的な解雇理由があり、かつ解雇が社会通念上相当と認められない限りは、たとえ「解雇」したとしても後に争われれば「無効」と判断されてしまうから(労働契約法16条)。私生活上の事情だけでは、かなりの事実(例えば刑事罰を受けたことのみの場合)があっても上記解雇事由に該たらないとした判例も多く、まして単に「勤務成績が悪い」などの理由では、最終的には程度問題ではありますが、なかなか解雇が認められることは難しいようです。
但し、解雇した配偶者の不倫相手が例えば同じ職場(会社や事業所等)の従業員であったような場合には、「職場内の不倫関係」を理由とした解雇を有効とした裁判例もあります。「不倫」という、あくまでも私生活上の問題ではありますが、不倫相手が同一職場だということによる職場への影響を考慮して、職場すなわち雇用関係上の問題であることを根拠に「解雇」も認める、という裁判所の判断ということです。
③ 退職させることができたとして、退職金や何等かの清算金・解決金の支払は必要か?
ア 配偶者が雇用関係にある従業員である場合
上記②の場合に退職金まで支払う必要があるかは、まずは就業規則に退職金規定があるか否か、ない場合には、過去に退職金の支払実績があるか否か、によって決められます。そして就業規則上の規定や支払実績がある場合には通常は支払う必要が出ますが、退職事由が「解雇」の場合には、例えば「懲戒解雇」の場合には全額を、諭旨解雇の場合には半額を、それぞれ支払わないものとするような規定があったりします。そのような規定がある場合には、解雇の種類によってそれに従うことになります。就業規則や支払実績のいずれもない場合には、退職金の請求権は、ほぼ認められません。
イ 配偶者が取締役等の役員に就任している場合
役員を退職させる場合には、上記と異なります。すなわち、役員との関係は委任契約(会社法330条)となりますので、委任者(ここでは会社)側から一方的に解除することができます。この解除のことを委任者からの「解任」といいますが、仮に会社の場合には、臨時株主総会を開催し、総株主の過半数が出席し、出席社員の過半数の賛同があれば解任できます(会社法339条1項)(会社によっては、定款により普通決議を上回るように定めている場合もあるので、定款の確認が必要となります)。
但し、上記の「解雇事由」ほど厳格なものは求められないとされてはいるものの、仮に「正当な理由」なく解任した場合には、解任時から任期満了時までの期間(次のとおり最長で2年近く)分の役員報酬を役員側から損害賠償請求される可能性があります(会社法339条2項)。
このように任期途中で上記「解任」する場合には、上記「正当な理由」が認められない場合には受任者(=役員)として何らの貢献もしていないのに期間満了までの報酬金を支払わなければならなくなり得る、というリスクを負います。
そうであれば、会社に影響がないことが前提ではありますが、期間満了までは「解任」せずに役員では居続けて貰い、ただ、期中では税務的に難しいかもしれませんが、少なくとも決算期が変わった時点で報酬金の引き下げと委任業務内容の変更を決議し、任期満了まで粘る役員側のメリットを無くしてしまうことで、自主的に役員(となった配偶者の側)から委任契約の解除(=「辞任」)をして貰うようにもっていく、という方法もあります。仮に上記の「辞任」はなく任期が満了となれば「再任」されることはまずないわけですから、取締役としての地位は失われることになります。
ちなみに会社の場合、任期は原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項本文)(委員会設置会社は1年(会社法332条3項))(※5)。
※5 但し、委員会設置会社以外の非公開会社においては、定款で10年以内の期間に伸長することができる(会社法332条2項)ことから定款の確認が必要となります。
(4) 高所得者のサラリーマンの方の場合の特色について
① 基本的には、次のような問題意識が必要です。
すなわち、
ア 収入が多いことから婚姻費用や養育費が多額になりがちです(一般的な「基本給」に加えて、ある程度のキャリアになると「職務手当」等もかなり多額に。
イ 経営者等のように経費を必要としないことから、婚姻中に蓄財ができていることも多いため、財産分与が多額となりがちです。
ウ 親権や監護権は未成熟児(小学生の中学年位まで)は母親が圧倒的に有利ですが、教育環境いかんによっては、父親に認められる可能性もあります。
特にサラリーマンに限らず夫が高学歴の場合には、監護・養育環境が整っていることを前提に、子の将来の進路に応じた教育環境は、他の家庭よりも親権・監護権者の認定にあたり重視される傾向にはあります。
エ 経営者等の方にも当然言えることではありますが、職場不倫等が離婚原因とされる場合には、職場での立場や同僚等への影響・評判や人事評価等にも関係してくることになる→次の②のように、これらに対する配慮が必要となります。
② 職場不倫における地位・評判等への配慮が必要なこと
事業所等に限らず、通常の職場でも「夫婦・男女問題を抱えている」ということ自体、マイナスの評価であり、ましてそれが職場での不倫ということになれば、それ自体が本業(経営者等としての業務)に悪影響を及ぼしているという判断をされ、社会的には致命傷にもなりかねません。
しかも、例えば、不倫相手側からすれば、配偶者のいる不倫相手に対し、このような職場でのスキャンダルは、恰好の交渉材料になり得ます。
そこで、このような不倫相手に対する対処は、決して対応に間違いのないよう専門家である弁護士に任せる方が安心です。
ア 不倫相手方側が不倫の事実を職場に公表・リークしようとしている場合→まずは専門家が交渉に入り、不倫相手方の要望内容を聞いてみる。意外と感情的なところが動機となっていることも多いため、誠意をもって対応すれば、和解(示談)により終了させることも十分に可能。
逆に話が通じない相手に対しては、上記の公表・リーク自体、名誉棄損罪や侮辱罪という犯罪が成立し得ること、公表・リークを材料に脅してきた場合には脅迫罪、金品を要求してくれば恐喝罪、義務のないことをさせられようとしたなら強要罪、例えば職場に押し掛けてきたりして職場での業務を妨害したりすれば業務妨害罪等の犯罪行為に該たる旨を説明して牽制する必要もあります。
イ 不倫相手が職場や自宅に今にも押し掛けて来ようか、という場合
→上記のとおり、犯罪にもなり得る旨を伝えて牽制する必要がありますが、何よりも、連絡等をテンポよくかつスピーディに行い、早期に示談を成立させることを最優先とした交渉をすべき
→不倫相手の気持ちや意見を積極的に聞いてあげることも必要に
→ほとんどの不倫相手が、要求できることの「相場」を理解しながら要求してきていることがほとんどなので、感情的にさせないようにさえ配慮すれば、意外と通常の範囲内で穏便に解決することができる可能性は高い
→とはいうものの、人によっては法外な要求をしてくる者もいるため、「相場」から余りにもかけ離れて当方に不利な条件は決して受け入れないこと=このような法外な要求は、通ればなおエスカレートすることが多いため、最初の段階できちんと「断る一線」を早めに設定して伝えておくべき→それでも行動に移す不倫相手に対しては、次の③の手続に。
③ 不倫相手側の行動によっては「面会強要禁止の仮処分」を裁判所に求める等の具体的方策が必要になります。
ア 面会強要禁止の仮処分であれば、裁判所が「一定のおそれ」があるものと認定してくれれば命令を出して貰えます。
イ DV防止法・ストーカー規制法の保護命令を求めていくことも有効です。
ウ 上記で各犯罪行為に該たり得る旨記載しましたが、これらはあくまでも「牽制」であり、警察が例えばこれら犯罪行為の被害者からの告訴に基づきすぐに動いてくれるかというと、被害内容が余程深刻でない限り、このような民間での出来事に対しては及び腰であることがほとんどです(良くも悪くも「民事不介入」は警察にとっては未だに存在する原則です)→だからこそ、上記②のアやイの手続を専門家に依頼した方が無難なのです!
④ 高所得のサラリーマンの高収入のほとんどは給与所得であるため、婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料のいずれでも、財産上の請求が関係する場合には、これらの請求権を被保全債権として、勤務先からの給料を(仮)差押されるリスクがあります。(仮)差押されれば、いうまでもありませんが勤務先に、否応なく少なくとも夫婦間の紛争の存在は知られてしまうことになります。
なお、仮差押の場合には、被保全債権額全額を「仮差押解放金」として積むことで仮差押を解除することを手続上はできますが、実務上は、仮差押までされてしまっている者が、解放金について、仮差押されてしまった対象財産以外の財産から調達することなどはなかなか難しいため、活用できないことも多いです。
4 経営者等の(未払)婚姻費用について
経営者等は、収入も多いし、ある程度の年数稼働してきていれば、それなりの資産も保有していることがほとんどです。→例えば、夫の側から離婚を望んだ場合、妻に自宅と預貯金の2分の1を渡せば十分であり離婚に速やかに応じて貰えるものと誤解していることがほとんどです。
しかし、妻側は専業主婦であることも多く離婚後の生活に不安を覚えることがほとんどである反面、経営者等である夫は離婚後も高収入であり、新しい女性との生活を始めることも可能であるなど、離婚に対して妻が持つ不公平感は夫側からの想像をはるかに超えていることが多いです。そのような離婚に不満をもつ妻側は、仮に夫婦関係は実質的に破綻していようが「婚姻」という身分関係だけは続けようと考えることになり、その最たる目的は、婚姻中に受領できる婚姻費用を継続して受領する生活ということになります。
確かに一般的に経営者等は高収入であるので、短期間であれば、実質的に破綻している夫婦生活のための婚姻費用であっても、支払い続ける余力はあるでしょう。
しかし、このような支払も長期間に及べば、支払っている夫の側の環境も変化していくでしょうし、例えば新しい女性が出来て再婚を望むような事態も十分にあり得ます。
そうなると、婚姻関係を継続しているために発生する婚姻費用の負担は、非常に重くのしかかることになりますし、仮に未払になってしまった分は、夫側の多額の負債としてその支払義務の負担が非常に重くなることになります。
そこで、まず、少なくとも婚姻関係が実質的に破綻してからは、できるだけ速やかな離婚を求めて専門家である弁護士に相談して離婚の示談交渉を始めるべき、ということになります。離婚示談交渉についての進め方については、離婚一般についての説明の項に譲りますが、次で述べるように、高収入の方の婚姻費用は相当な金額に上ることからすれば、一刻も早くこの負担から法律上免れるために離婚を成立させる必要があります。
(1) 年収が2000万円を超える場合
実務上、婚姻費用の算定については算定表(家庭裁判所における標準的算定方式とこれを元にした簡易算定表)を用います。ちなみに、簡易算定表の金額は、夫婦それぞれの収入の金額と、夫婦間の子の人数とその年齢を要素として決められています。しかし、この算定表上は給与所得者であれば年収2000万円まで、事業所得者であれば年収1567万円(令和元年12月の改訂前は1409万円)までしか記載されておりません。そのため、この記載を超えた収入の支払義務者の場合に、上記標準的算定方式をそのまま適用して算定してよいか否かは次のとおり争いがあり、現実には、多くの裁判例でも統一されておりません。
〔算定表上の記載の金額(上記でいえば2000万円等)を上限とすべきとする説〕
義務者の年収が2000万円(但し、給与所得者の場合。事業所得者は上記のとおり1567万円)もある場合、仮に妻の年収が0円の場合には月額30~32万円が認められる(夫婦のみの場合。なお※6)から、婚姻費用としてこれを上限として考えても、かなり余裕のある生活ができるという発想に基づいているものと思われます。
※6令和元年12月に、上記家庭裁判所の算定表は改訂されていて月額も若干増減しております。
〔上記2000万円等を上限とはしないで同じ算式を用いて算定すべきとする説〕
上記場合を例に取れば、仮に「夫婦のみ」の場合でも上記30~32万円でも十分とは考えずに、上記の標準的算定方式をそのまま適用して算定すべきとする考え方です。
簡単な例で算定してみましょう。
給与所得者の場合として、年収(総収入。源泉徴収票中の「支払額」)3000万円として、係数(0.38~0.54なお※7)を乗じたもの=基礎収入(=実際の収入から公租公課、職業費、特別経費等を控除したもの)…上記算定方式は簡易迅速に算定するために、統計等に基づいて上記公租公課等を係数として概算で上記範囲で乗じて基礎収入を算出することにしています。
上記係数に0.38~0.54と幅があるのは、上記公租公課等も、必ずしも所得額に応じて比例するわけではないためです。すなわち、所得が上がるにつれて公租公課も同じ割合で上昇するものではない(=累進課税ではあるが、必ずしも収入や所得に比例するわけではない)ので、高額所得者ほど、基礎収入の金額は多くなっても、収入や所得に占める割合は低くなります。
※7令和元年12月に、上記家庭裁判所の算定表は改訂されていて上記係数も若干増減しております。
上記基礎収入に生活費係数を乗じます。なお、生活費係数も、簡易迅速に算定するために統計等に基づいて計算され指数化されたものであり、この基礎収入で生活することになる被扶養者の年齢によって決められています。ちなみに、親を100とした場合に、子のうち0~14歳は62、15歳以上が85とされています。なお※8
※8令和元年12月に、上記家庭裁判所の算定表は改訂されていて上記係数も若干増減しております。
仮に、上記の妻だけの場合を算定してみますが、基礎収入割合を上記0.38~0.54の平均値である0.46で試算してみると、婚姻費用Z=(X+Y)×(100)÷(100+100)…Xは義務者(夫)の基礎収入、Yは権利者(妻)の基礎収入
従って、(3000万円×0.46+0円)×100/200=690万円=Z
Z-Y(権利者の基礎収入=0円)=690万円÷12か月=57万5000円となり、(上記2000万円から3000万円への)1000万円の年収増加に対し、月額25万5000円~27万5000円もの増加となります。
上記上限の有無についてはどちらの考え方が一律正しいか否かは言えないですが、いずれにせよ、特に上記のように上限を超えているために簡易算定表には記載されずに上記算式による算出まで要する場合には、変数の要素もある各係数も用いたそれなりに複雑な計算が必要となりますので、専門家である弁護士にご相談下さい。
なお、上記試算は夫婦のみの場合ですが、子が複数いたりすれば更に複雑な計算になります。また、上記では話を簡単にするために、専業主婦の妻は収入0円で計算していましたが、特に最近では、稼働可能性がある限り、学歴等に基づいた賃金センサス所定程度の収入を得られるであろうことを前提に妻側にも基礎収入を認めて算定する場合がほとんどといえます。
(2) 年収が2000万円未満の場合
上記のとおり、子の人数と年齢に応じて簡易算定表から算定します。
ポイントは、夫婦のそれぞれが給与所得者か事業所得者か、に応じて、婚姻費用を求める側が「権利者(=横軸)」、求められる側が「義務者(=縦軸)」の各年収(算定表の場合、収入そのもの=給与所得者なら源泉徴収票中の「支払額」、事業所得者なら確定申告書中の「所得額」※9)に応じて該当する(縦軸と横軸の)交点を探し、その交点が属する金額帯(ベルト)の範囲で決められます。
あとは、子の人数と年齢に応じて該当する表を探すことになります。
万が一、簡易算定表中に該当する表がない(例えば子の人数が更に多くて該当する表がない等)場合には、上記(1)と同様に、算定式により算出しなければなりません。
この場合には、専門家の弁護士にご相談下さい。
※9 高所得のサラリーマンの方で様々な控除があったり、例えば勤務先から借入をしていて給料からの天引きで返済しているような場合には、手取額は少ないのに婚姻費用の算出基準収入額は高くなってしまい、到底支払えないような額の婚姻費用を認定される場合もあるので注意が必要です。
(3) 経営者等の場合、役員報酬(=会社の役員の場合)、給与収入(=ほかの会社での顧問や嘱託社員等の場合)以外にも次のとおり収入ないし所得がある場合があります。これらの収入・所得は、婚姻費用の算定にあたり、全て合算されることになります。よって、漏れなく計上する必要があります。これらの所得をきちんと申告しているのであれば、確定申告書が最大の手掛かりです。
但し、これらの所得を生み出している元が特有財産の場合には、婚姻費用算定の際の基礎にする収入に含めるべきかについては争いがあります。当該「夫婦」と「婚姻生活」の実情に応じて個別・具体的に判断されるべきものと思われます。
① 他の会社等法人等にも勤務している場合(アルバイト・非常勤・派遣勤務等も含めた給与所得)
② 不動産を自己の事業所その他に賃貸している場合(賃料からの不動産所得)
③ 株式等からの配当がある場合(配当所得)
④ 不動産・株式等の売却益がある場合(譲渡所得)
⑤ 公社債等の利子、合同運用信託の収益分配がある場合(利子所得)
なお、特に離婚紛争となった後等に事業所が会社等法人化したような場合に、婚姻費用の算定の基礎となる夫の収入について、法人からの役員報酬だけでなく、法人の売上も算定の基礎となる収入に入れるべきだ、と妻側から主張されることがままあります。
最終的には、上記法人からの報酬額と法人の売上金額との相関関係で結論が出される側面はあるでしょうが、例えば裁判所は通常は、形式を、ある意味一般社会以上にむしろ重視しますので、役員報酬を超えて法人の売上金額までも算定の基礎とすることは相当難しいものと考えられます。この形式重視の点は、財産分与についても、夫名義と法人名義とで、裁判所は割と厳格に判断しています。
ところで、財産分与において、会社等法人に対する妻の持分を、夫ないし会社等法人が買い取る場合、夫にも会社等法人にも買い取るだけの資金が不足している場合が、特に昨今の不況下では、ままあります。
このような場合、財産分与を要求することで会社等法人ないし夫を倒産までさせることは、離婚後の養育費も受領できなくなるし、何よりも経営者等が業務を継続して、場合によっては子に会社や事業所を承継させることを妻側も望んでいる場合も多いです、このような場合には、交渉により、妻の会社等法人の持分分の譲渡代金の請求は放棄ないし免除して貰うことが可能な場合が多いものと言えます。
婚姻費用の継続支払を狙い離婚に応じない妻に対しては、離婚の財産分与時にいわば「扶養的財産分与」として、一定期間妻の生活費を負担するような条件を提案すると離婚に応じて貰える場合も多いです。
本来であれば、離婚後は(むしろ子のための)養育費を受領できるだけなのが原則なので、裁判所に判断を仰ぐ場合でも、離婚後は元妻の生活費の分担請求は当然には出来ないことがいわば説得材料となる訳です。但し、余りに高額の扶養的財産分与をすると、夫から妻への「贈与」と認定され、妻に贈与税が課税されるリスクもあるので注意が必要です。
5 経営者等の養育費について
(1) 通常の場合
算定表や算定式が養育費に変わるだけで、基本的には婚姻費用のところで述べたことが、ほぼ該当します。但し、養育費は、あくまでも離婚後の問題なので、算出される生活費も、あくまでも子のものに限られ、離婚した(元)妻の分は含まれません。
よって、算定月額も、婚姻費用よりも養育費の方が少額となります。なお、妻の生活費分が含まれるためには扶養的財産分与等として財産分与の中で考える他ありません。特に経営者等の方の場合には、婚姻中は妻も相当多額の生活費を受領してきた関係上、生活費(婚姻費用)を受領し続けたいが余り離婚に応じてもらいにくい点は前述しましたが、これは、このように、養育費には(元)妻分の生活費は含まれないことが影響しているのです。
(2) 子が海外留学等を目指す場合等
まず、養育費(婚姻費用もここでは同じです)と別に「留学費用」の支払を求めることは、いくら親が経営者等でも当然に認められるわけではありません。換言すれば、算定表等によって定められる養育費(婚姻費用につき同上)には、このような「留学費用」も、一般的な範囲でならば含められています(だからこそ、令和元年12月の算定表の改定時には、公立高校の無償化の影響も受けた改定部分もあるわけです)。
ところが、経営者等の場合には、養育費等の支払義務者が留学に承諾した場合はもちろん(自身の経歴から承諾する方も当然多いものとは思われます)、仮に承諾がない場合でも、子の父母双方の収入・経歴・地位等に応じて合理的な範囲で「留学費用や各種教育費」も費用負担を認められる場合があります。一例として、例えば両親ともに貿易商の場合に、海外留学費用までの支払義務が家庭裁判所で認められたケースもあります。以下では、もう少し具体的に検討してみます。
① 国内の大学(高校・中学等)の費用負担について
支払義務者の承諾があれば負担が認められることは上記のとおりです。
この承諾がない場合に負担が認められるかは一概にはいえませんが、支払義務者権利者の各経歴(に基づく収入や地位)、一般的には決め手とはなり得ないものの、参考までに支払義務者の親等の経歴等により負担の肯否を若干ステレオタイプ気味に整理すると次のような関係に立つものと思われます。(負担が認められる・・・〇、少々多額でも認められ得る…◎、認められない…×、どちらともいえない…△)
右記の各人の経歴等 支払義務者 支払権利者 (参考)
支払義務者の親等
国内の大学(高校・中学等)出身 〇 △ 〇
海外の大学(高校・中学等)出身 ◎ 〇 ◎
② 海外の大学(高校・中学等)の費用負担について
支払義務者の承諾がある場合は上記①と同じです。
但し、特に海外の大学でも、例えばアメリカ合衆国の経営大学院(MBA等取得のため)の場合には、学費が2年間の総額で数千万円となることも珍しくありません。よって、仮に法律上養育費の負担が認められても、支払義務者の資力ないし支払能力の方が問題となります。この点は、金額の面では次の③の場合とは比較になりません。
次の(ステレオタイプ)整理においてもこの点は注意を要します。(なお各記号の意味は同上)
右記の各人の経歴等 支払義務者 支払権利者 (参考)
支払義務者の親等
国内の大学(高校・中学等)出身 △ないし×
(支払能力等次第) × △ないし×
(資力等次第)
海外の大学(高校・中学等)出身 〇 △
(支払義務者次第) ◎
③ 留学のための予備校や塾について
支払義務者の承諾がある場合は上記①②と同じです。
金額についても、上記アメリカの経営大学院の学費総額ほどにはならないとしても、外国資本の優良企業等への就職を目指す等して敢えて多額の費用を(いわば「先行投資」として)予備校や塾に費やす家庭も増えています。経営者等に限った話ではありませんが、就業してからも毎日が研修の日々であることに鑑みれば、遅くとも高校時代までには「学習」に対する意欲・能力を備えて、海外の有名大学等に留学する、そのためには予備校や塾に費やす金額には糸目は付けないというのも、経済力の有無にかかわらず、ご家庭ないし両親の一つの考え方だと思われます。
右記の各人の経歴等 支払義務者 支払権利者 (参考)
支払義務者の親等
国内の大学(高校・中学等)出身 △ないし〇
(自らの経験等による) ×ないし△(支払義務者(の経験等)次第) ×ないし△
(自らの経験等による)
海外の大学(高校・中学等)出身 〇ないし◎
(同上) △ないし〇
(同上) 〇ないし◎
(同上)
6 経営者等の親権・監護権(お子様へのケア)について
特に会社等の経営者の方の場合には、子を後継者として想定することが一般的です。この場合、例えば夫側が会社を経営している場合に、離婚に伴う親権・監護権を夫側が取得することを強く希望する場合が多いです。もちろん、親側の都合で単に「後継者にしたいから」という理由だけでは親権・監護権者の指定はなされません。特に未成熟子の場合には、このような場合でも親権・監護権の取得は母親側が有利な場合が多いです。
しかし、あくまでも「子の福祉」が親権・監護権を指定する際の唯一の基準ですので、
子の生育・教育環境の面で余りに極端に差があったりする場合には、母親(妻)側といえども親権・監護権を取得できない場合もあり得ます。逆に父親(夫)側としては、経済力の面で自己が有利であることは当然として、監護補助者の存在等も含めて、上記の生育・監護環境に加え、自分(たち側)の監護能力や適性、監護の実績等を積み上げるといった事実関係の準備から入念に行うべきものといえます。夫婦双方とも、親権・監護権を争う場合には、専門家である弁護士に依頼をして、このような準備段階から、しっかりとアドバイスを受けることも肝要です。
上記争いへの備えという点では上記のとおりですが、離婚という夫婦間の紛争により最も傷付くのは、通常はどちらの立場にも立ち得ない子であることは間違いありません。
あくまでも紛争の相手方は夫婦のどちらか他方なのであって、子の処遇については、「子の福祉」のために最適になるように考えてあげることが必要です。家庭裁判所も、「子の福祉」を考えるにあたっての4原則(※10)を基本として親権・監護権者等の指定の判断要素・基準としております。
なお、仮に子が、相手方配偶者の下で生活していたりして、同配偶者の意向が子の人格形成に相当な影響を与えていると思われ、これを快く感じない他方配偶者も多いものと思われます。しかし、子というのは、未成熟ゆえ最も身近な者に親近性を覚えるのみにとどまらず、自己保身のために、近親者の大人に順応していくという特性があります。よって、相手方配偶者の下にいる際の子の言動のみによってその子の本質と判断するのは早計です。
子の本質を見抜いていくためには、例えば監護・養育環境を変えることも重要ですし、何よりも、中立かつ公正なはずの家庭裁判所調査官等の調査等を経ることも重要です。調査官は児童心理等にも通じていることから、子の表面的な態度からだけでは判断しないことも多いです。
※10 家庭裁判所が「子の福祉(利益)」を考えるにあたっての4原則(=親権者・監護権者指定にあたり、これまでの裁判の蓄積で形成されてきた判断要素と判断基準です)。
具体的には、
① 継続性の原則…実際にその時点までに子を監護してきた者を優先するという原則です。子の通学先や友人関係を含めた環境を、離婚する親の事情でできるだけ変えないほうが望ましい、ということから「現状維持を重視する」ものです。
特に経営者等の離婚においては、子が開業等を目指して海外の経営大学院等への留学を考えたりすることが多いので、その進学のための学習環境を変えることは望ましくない、という形で、判断に大きな影響を与える可能性があります。
② 子の意思の尊重…実務的には10歳程度以上の子に対しては家庭裁判所調査官の意見聴取が行われ、その発言及びそれから表明された意思が持つ深い意味まで吟味された上で、基本的には尊重されるが、客観的に(=いわゆる「常識」として)子の利益に反する場合は尊重されない場合もあります。
特に経営者等の離婚においては、子の精神的成熟が、子の学力や自主・自律性、将来の目標へ向かっての態度(真摯さ)に比例して、進んでいることが多いため、比較的年齢が小さい子でも、その意思は尊重されやすいだろうと思われますし、尊重されるべきものとも思われます。
③ 兄弟姉妹不分離の原則…一昔前なら、長男を夫が、長女を妻がそれぞれ親権者・監護権者として引き取る、という解決策も多く、現在でも協議・調停という、両当事者の合意によって離婚する場合にこのような解決をする夫婦もいないわけではありません。
しかし、家庭裁判所が判断する場合には、兄弟姉妹は一緒に監護・養育することが、子らの人格形成にあたり、子相互に「経験を共有」できたりもすることから、特に社会性の獲得等のために好い影響を与えることも多いため望ましいとされています。
但し、経営者等の離婚においては、比較的早い段階から将来の海外での活躍等目標を定めて勉学に励むために、例えば中学等から国外の全寮制の中高一貫の進学校に入学したりするケースも多く、そうすると、兄弟姉妹といっても必ずしも同じ居住場所で共に過ごす、というパターンばかりではないことも多くみられるものと思われます。
あるいは、例えば夫または妻(ないしは両者の実家)が会社を経営している場合には、何が何でも長男の親権・監護権を取得して引き取って育てたいという要望が強かったりして、長男とそれ以外の子で親権者・監護権が分けられる、という解決もありえます。
但し、前者のように、すでに全寮制の学校での生活のように環境が整っている場合には上記①の継続性の原則からも、必ずしも兄弟姉妹不分離に固執されることはないでしょうが、「会社の跡継ぎにしたい」という要望はあくまでも親側の事情に過ぎないので、仮に家庭裁判所が判断する場合には、その点だけを重視して敢えて兄弟姉妹不分離の原則に反する決定をしてくれる保障はありません。従って、上記「跡継ぎ」としてどうしても長男を、という要望を実現させるためには早い段階から長男の学習環境を進学先等も含めて入念に整え、そのような環境は、例えば夫(ないしはその実家)側でない限り整えることはできない等の準備を(親権・監護権紛争の起きるかなり前から)しておく必要があります。
④ 母親(母性)優先の原則…特に子供の年齢が低い場合は、母親が育てることが望ましいという考え方です。身体的性差(例えば授乳等)にも根拠がありますが、一定年齢に達するまでは母性からの愛情が必要で、それが人格形成にあたって他者への思いやりやいたわり等を育む点等が指摘されています。
しかし、近年では、上記授乳の点すらも哺乳瓶や粉ミルク等の普及により男性でも問題ないようになってきており、子の養育・監護の面でも男女平等の考え方がかなり一般的となってきておりますので、以前ほどは重視されなくなっております。
従いまして、経営者等の離婚においても、例えば子の年齢が低い未成熟子で妻側に親権・監護権が認められやすい状況には一般的にはあっても、特に現在かつ将来の進学・学習環境等を整えることができ、夫の母や姉妹等の監護補助者もいて情操教育上等も問題がないと判断されるような事情があるなら、夫側に親権・監護権を認めさせることも完全に不可能というわけではありませんので、専門家としての弁護士にご相談頂ければと思います。
なお、特にこの4つ目の原則に関係して、参考までに、年齢別における妻(母)側に親権・監護権が認められる可能性を記載しておきます。
子の年齢別の親権・監護権者の簡易判断方法
ア 0~10歳(子の年齢) 母が指定される可能性が高い。
イ 10~15歳 父・母に優劣が付けられない場合には母とされる可能性が高い。
ウ 15~20歳 子供自身の意見が尊重される。
エ 20歳以上 成人に達しているので親権者を決める必要はない。
親権が存続するのは子供が20歳になるまでである。
※民法第4条、818条1項
7 経営者等の面接交渉権について
親権・監護権を有しないこととなった配偶者(通常は夫であることが多いものと思われます)は、他方配偶者に対して子との面接交渉(面会交流)を求めることができます。この場合、経営者等に限らず「月1回程度、子の福祉に反しない方法・態様で面会させる。なお、面会の具体的日時・場所は事前に当事者間で協議して定める」位を決められるのが一般的です。
しかし、仮に面接交渉を求めるのが経営者等である父であったりする場合には、①そもそも経営者等で多忙であること②子の成長等において、例えば学習等の到達度に対する関心が高くなりがちであること③進学先について、海外留学等を希望するのかについても重要な要素であることも多いこと等々から、一般の場合より諸事情に配慮しながら面接交渉を充実させる必要がある場合も多くなるものと思われます。このような場合には交換条件ではありませんが、上記養育費のところで触れた、海外の大学や大学院、そのための進学塾の学費等の負担を特別に求めること等も一つの解決策ではあります。
弁護士 鈴木軌士
最新記事 by 弁護士 鈴木軌士 (全て見る)
- 年末年始のお知らせ - 2021年12月29日
- 年末年始のお休みのお知らせ - 2020年12月25日
- オンライン面談導入のご報告 - 2020年4月20日